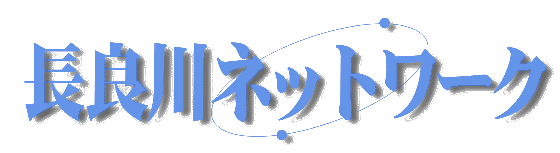
|
変貌させられた長良川の現状! 「長良川研究フォーラム」での報告から |
| 岐阜大学地域科学部教授 長良川下流域生物相調査団 粕谷志郎 |
昨年の11月22日、岐阜市の長良川国際会議場で、長良川の現状を科学的に討議する、第四回「長良川研究フォーラム」が開催された。これは、いくつかの研究クループが、それぞれ独自の調査研究を毎年発表してきたもので、堰運用後3年以上を経過した長良川の変貌を具体的・科学的に把握する責重なデータを提供している。これらの報告をまとめてみた。
藻類の大発生=長良川河口堰事業モニタリング調査グループ
東海大橋では河口堰運用前はクロロフィルaの大量発生のピークは観察されなかった。堰の完成後ピークが見られるようになり、95年の本格運用になった後はリッターあたり80マイクログラムを越すピークが出現した。97年、98年は出水が多く、ピークは小さい。一方、伊勢大橋では、調査開始の90年より夏期に一過性にリッターあたり40−80マイクログラムのピークが見られていたが、堰運用後は、多ピークの発生に転じている。これらの変化は、日照時間、雨量、水道、リン、窒素量に大きな変化が認められなかったことより、堰運用による変化と断定できた。また、今まであまりよく知られていなかった、ワムシの発生時期にクロロフィルaが減少し、居なくなると増加することもわかり、ワムシによる藻類の捕食も明らかとなった。今年から、長良川の水が配水された地区で、異臭についての苦情と、浄水場での活性炭の注入の騒ぎが報道された。水道水源として適格であるかどうかは、安全性とともに浄水のコストも考慮し、議論されなければならない。
堰上下流での著しいヘドロの堆積=長良川河口堰事業モニタリング調査グループ
ヘドロの定義をきちんとしておく必要がある。砂が少なく粒子が細かい(シルト・粘土に相当し、径0.05ミリ以下)、有機物を多く含み、強熱減量が5%以上である底質を指す。堰の上下流とも3キロメートルほど手前よりシルト・粘土の堆積が明瞭になり、堰に近づくほどシルト・粘土の堆積が厚くなる。強熱減量も堰に近づくほど、上下流とも高くなり、6−8%に達する。川底の超音波探査では、200キロヘルツが主に泥に反射し、50キロヘルツが主に砂に反射する性質を利用し、その差を観察したところ、両波長で最大50・60センチメートルの差が確認できた。実際のシルト・枯士の堆積厚はちょうどこれを2倍した程度であることもわかった。従って、長良川では50−100センチメートルの泥が溜まっている。
へドロは最大2メートル=長良川下流域生物相調査団
200キロヘルツの魚群探知機により、堰運用前と最近の、河口堰下流の河床を探査し、堆積厚を計算した。基準点は、それぞれの海水面のT.Pをそろえ、水深を測る方法と、堰コンクリート位置をそろえる方法でも行ったが、いずれの方法もほとんど差はなく、それによると、平均1.2メートル、最大2メートルの堆積厚であった。堆積厚の特に多い地点は、河口より3.5キロメートルから、河口堰までであった。強熱減量は4.5キロメートル地点で、10%と、多くの有機物の含有が確認できた。また、このヘドロは粘着性が高いため、1100立方メートル程度の洪水ではほとんど流失することはなく、今後も堆積しつづけるものと予想された。
ヤマトシジミに次いでマシジミも居なくなった=しじみプロジェクト・桑名
堰上下流で、ジョレン式採集装置で、シジミを採集し、種類や量を経時的に観察してきた。河口堰近くの揖斐川では、季節変動は見られるものの、毎年、同じような傾向が見られた。長良川の堰下流500メートルでは、95年7月を境に、採集できるものは全てゴミとなった。堰上流700メートルでは、97年までは、従来どおり採集できたが、今年に入って採集量はほとんどゼロになった。堰上流3600メートルにおいても、同様の傾向であった。マウンド(堰上流10.6キロメートル)でも、今年8月は大部分がゴミとなった。なお、この地点でのヤマトシジミは、95年は、大部分であったが、96年あたりから急に減少し始めた。97年8月には8−9割がマシジミに変わっていた。そのマシジミも98年からはほとんど採れなくなって、ゴミぱかりとなった。一個体あたりのシジミの重量を計ると、ヤマトシジミは堰閉鎖後、徐々に増加し、新たな個体の発生が無いことを物語っている。マシジミは当初横這いであったが、97年より直線的に増加していることより、97年ころから、新しい個体の発生が無くなったことが、示唆された。堰上流も、堆積物やゴミのため、淡水性のマシジミですら棲患できなくなっている。なお、三川の漁獲高の質問に対し、揖斐川から長良川ヘヤマトシジミを放流している(例年300トン、今年は70−90トン)が、放流分も採れていない。今は、一艘も長良川ヘシジミ漁に出かけていない。かつて、一艘あたりの限度である180キログラム〜200キログラムの漁獲は一回20分程度の作業で獲れていた。今は、揖斐川で漁を行っているが、4−5回は作業しなければ達しない。しかも、死貝が多く、質は悪くなった。
環形動物のみ生き残る下流=長良川下流域生物相調査団
堰下流の底生動物の調査では、ヤマトシジミは右岸と左岸の浅瀬と、人工的「渚プラン」なる4キロメートルあたりに細々と棲息しているにすぎない。下流で優占な動物は多毛頬などの環形動物であった。この数は増加の傾向にあった。
野鳥の変化は二度起こった=日本野鳥の会
1998年の県下で観察されたカモ類の38%が、長良川下流域に観られ、17種を記録した。96年は過去10年間で最も多い羽数を記録した。これは、カルガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、キンクロハジロの増加による。中でも著しい増加はキンクロハジロであった。キンクロハジロ、ホシハジロは湖沼性のカモ類で、前者は二枚貝を、後者は藻を主食としている。河口堰が閉鎖され、こうした湖沼性のカモ類の増加が著明になった。しかし、今年に入り、キンクロハジロが激減している。これは、利根川でも確認されたことであるが、二枚貝の減少と強く相関している。
仔魚降下は5分の1以下に=長良川下流域生物相調査団
仔アユの降下密度は18キロメートル地点から、6キロメートル(河口堰直上)までの間に、5分の1以下に減少した。仔魚の体長は41キロメートル地点で0.65−0.70ミリメートル、6キロメートル地点で1.00−1.05ミリメートルが最も多かったが、下流に行くに従って、体長のばらつきは大きくなった。耳石による日令の推定では、41キロメートルでは平均1.4日、10キロメートルでは平均13、4日、最も多いのは12−15日令、しかし、22−24日の個体も認められた。河口堰の湛水域を降下するにはかなりの日数を要することが明らかとなった。通常の河川では孵化後数日で海に到達するものと考えられている。また、孵化後5日以内に摂餌可能な水域に達しないと生残できない。降下日数の増加が、仔魚密度の極端な低下の要因となっていることは明らかである。
仔アユの工サに乏しい堰湖=長良川下流域生物相調査団
18キロメートル地点の降下仔アユ61.3%が空胃で、通常のエサである動物性プランクトンを食べていたのはわずか15.5%であった。19.2%が藻類を食べていた。この地点の日令は6日前後であり、本来活発な摂餌活動をする時期である。堰閉鎖により、淡水化したことで、動物性プランクトンの数は激減した。このため、摂餌がかなり制限されているものと考えられた。6キロメートル地点は餌環境はかなり良い状態であるが、十分エサを取れる個体とすでに衰弱し、エサをとれない個体とに分かれる状況が見られた。
天然溯上鮎は何処へ?=長良川下流域生物相調査団
長良川三漁協(長良川、長良川中央、郡上)の漁獲高は、93年の冷夏で著しく落ち込み、94年に若干回復したが、95年以降再び落ち込んだままである。この中で、長良川漁協(最下流)のみが、放流漁獲高の50%以下の漁獲高しかない。他の漁協は両者がほぼ等しい。郡上漁協では93年の落ち込みは軽微で、95年以後も他の漁協の落ち込みに比べて影響が少ない。このことは、もともと放流魚に依存する割合が高かったものと考えられた。一方、揖斐川中部漁協では、漁獲高は93−94年に減少したが、その後、ほぽ回復している。しかも、漁獲高は放流漁獲高を大きく上回っており、天然溯上がかなりを占めるものと考えられた。根尾川筋漁協は、94年以降、漁獲高はほぽ完全に回復した。漁獲高は放流漁獲高を常時下回っている。しかし、84年以前は、漁獲高が放流漁獲高を上回っていたことから、昔は天然溯上があったものと推定された。
ゲートが開いてもサツキマスは溯らない=サツキマス研究会
38キロメートル地点のサツキマス漁獲高から見ると、堰運用によって、サツキマスの溯上の遅れが指摘できる。ちょうど半数の漁獲が達成した日付をみると、運用前は、5月上〜中旬であったが、運用後は、中〜下旬にずれこんでいる。96、97年は溯上期に、出水によるゲートの全開が各1回あり、その後に、漁獲が急増した。98年は、3回ゲートを全開しているが、その後の漁獲の増加は全く見られなかった。このことは、ゲートが物理的障壁になっていない可能性が出てきた。障壁になるほど多くの溯上が無いとの見方もできる。
さようなら!ベンケイガニ=長良川下流域生物相調査団
98年9月、15キロメートル地点右岸と18キロメートル地点左岸の長良川と18キロメートル地点木曽川右岸で、3名が30分間見つけ取りを行った。この結果、長良川15キロメートルでは36匹、18キロメートルでは44匹が、木曽川18キロメートルでは218匹が確認できた。長良川のベンケイガニの体長はすべて7.1ミリメートルを上回った。木曽川では約半数が、このサイズより小さかった。このことより、堰運用後に長良川を溯上したベンケイガニは居なく、以前に堰上流に来たベンケイガニの一部が生残しているのみとなったことが示唆された。
カワヒバリガイは90年頃より居着いた=新村
淡水産のカウヒバリガイは、日本には居なかったが、1993年に長良川で初めて見つかった。90年頃にはすでに入っていたものと推定される。3メートルより水深の浅い所を好み、それより深い所は、塩水にも強いコウロエンカワヒバリガイが占める。給水管に付着し、浮遊幼生を生み落とす。塩素注入で死ぬが、末端で1ppmが必要。韓国では、この処理で水道水がまずくなった。塩素処理のため、工業、農業には使えず、飲用のみとなる。
支川から流入し、増殖するユスリカ=長艮川下流域生物相調査団
堰運用前は、6−10キロメートルあたりは、塩水が遡上することから、塩水に強い2種類のユスリカが、極少数採集されたのみであったが、運用により淡水化したため、0.25平方メートルあたり、数百匹にのぼる幼虫が認められるようになった。しかも、汚染水域に多いセスジユスリカが優占となった地点も出現した。これらは、34キロメートル地点に流入する支川より供給されることが明らかとなった。しかも、この辺りで大量増殖したセスジユスリカは、出水で、堰湖全体に配られるという、大量発生のメカニズムの一端が明らかとなった。
 河口堰直下に堆積したヘドロを見る長良川中央漁協有志の人たち(1998年4月)
河口堰直下に堆積したヘドロを見る長良川中央漁協有志の人たち(1998年4月)
| Page 1・2・3 | ネットワーク INDEX | HOME |