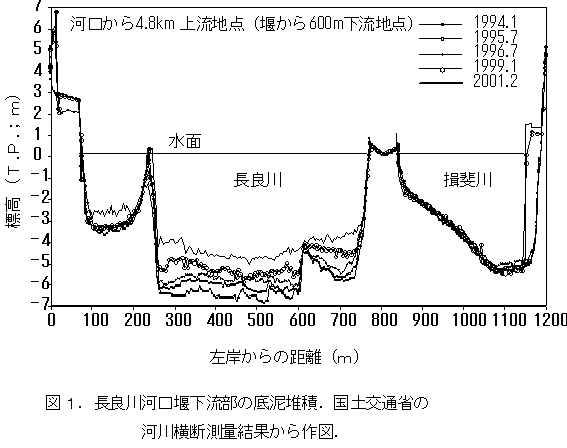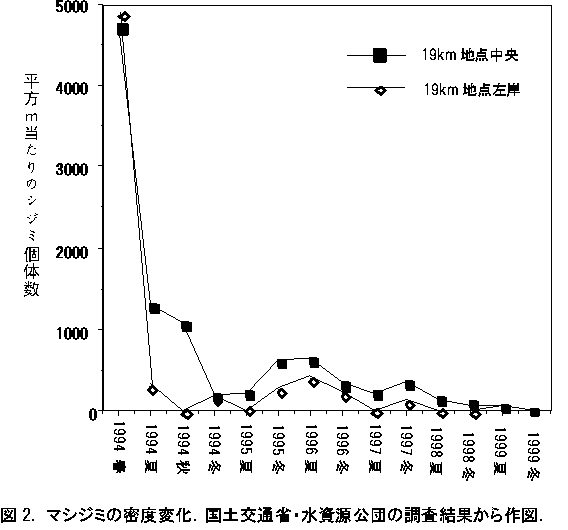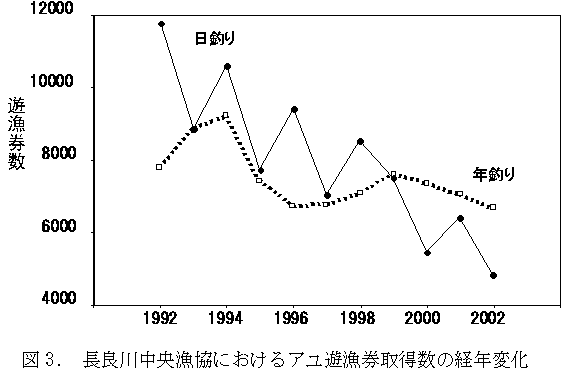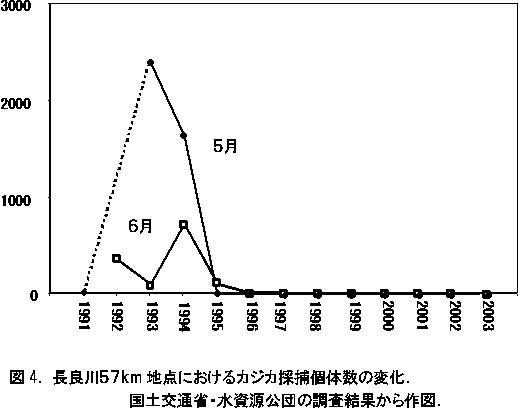VOL31-3
VOL31-3
運用10年後の検証
汽水域の破壊・河川の湖沼化・人工水路化。
河口堰運用後の長良川における自然・環境の変化 |
長良川下流域生物相調査団・山内克典
|
長良川河口堰が運用されて10年が過ぎた。
堰運用後5年間に起きた自然環境の変化は、日本自然保護協会の報告書や
学会誌掲載の諸論文などで次第に明らかにされてきている。
簡潔にいえば、それは汽水域の破壊であり、
河川の湖沼化であり、さらに人口水路化であろう。
ここでは、その後の調査・検討で得られた点も含め、若干の問題について述べる。
河口堰下流部の大規模ヘドロ堆積
河口堰運用前後に大きな論争となった堰下流部における底泥堆積問題は、
実際に生じた大規模な底泥堆積によって決着がついている。
多くの調査・研究が底泥堆積の事実を明らかにしているが、
ここでは、国土交通省による河川横断測量から得られた堆積の様子を示す。
国土交通省では1、2年に一回、200m間隔で河川横断測量を行っている。
図1は堰下流600m地点の測量結果である。長良川と揖斐川を比べてほしい。
揖斐川では、1994〜2001年の7年間、河床高にほとんど変化がないのに、
長良川では年々堆積が進み、同期間に約2m浅くなっている。
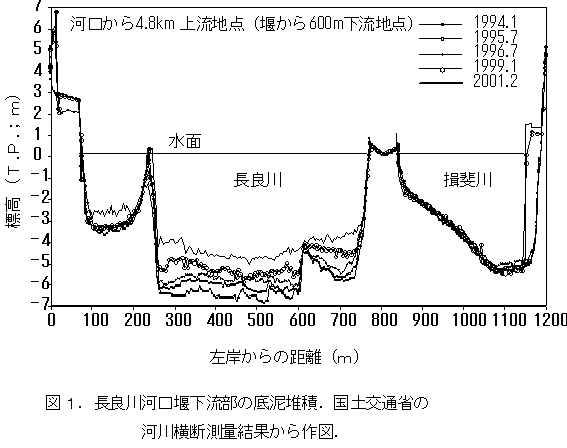
堰の下流0.2〜1.6km(河口から3.8〜5.2 km)間に堆積した底泥の量は
7年間で約102万立方メートルに達したと推定される(東京ドームの容積、約124万立方メートル)。
これは、出水時以外は多量の有機物を含む黒色軟泥(ヘドロ)が堆積し、
大規模出水時には、ヘドロは流されることなく、その上に砂が堆積する。
その繰り返しの結果である。
最近では、底泥堆積域はより下流部(堰から約2.5km下流地点)まで拡大していることが
私たちの調査で分かっている。堰下流部の環境変化によってヤマトシジミは激減し、
現在、長良川のシジミ漁はほとんど行われていない。
河口堰は堰上流部の汽水域を消滅させただけでなく、
下流部においても汽水域の環境に大きな影響を及ぼした。
マシジミの減少
河口堰運用によって広大な汽水域の大部分は淡水に変わった。
したがって、ヤマトシジミ、ゴカイ類、カニ類などの多くの汽水性動物は堰上流では消滅した。
広大なヨシ原も湛水の影響により激減した。
いっぽう、淡水産のマシジミは増加すると考えられ、ヤマトシジミの代替産物として試食会なども行われた。
しかし、現実には、マシジミ密度は年々減少した(図2)。
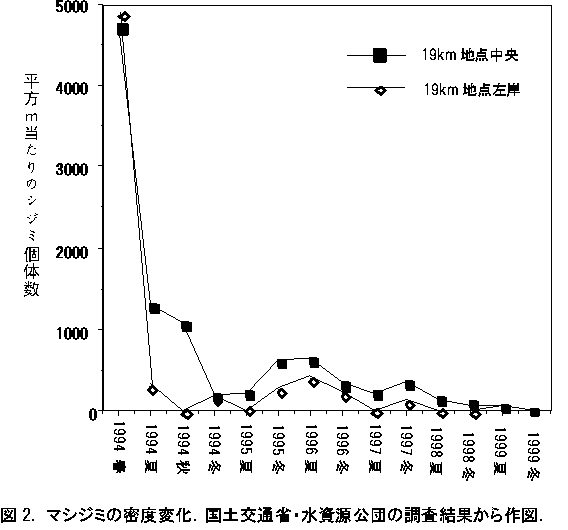
マシジミがかつて高密度で生息していた水域は、
国土交通省・水資源開発公団による自動水質観測の結果などを分析したところ、
堰運用後も顕著な底質悪化や溶存酸素量の減少が認められないことが分かった。
密度減少の要因として、洪水時におけるシジミの流下が考えられる。
川底浚渫やブランケット造成などの河道整備によって、洪水時の流速は大幅に増加した
(洪水時における長良川と揖斐川の流速について、岐阜大学の藤田氏がモデル解析により明らかにしている)。
このことは洪水の水位を低下させるが、いっぽうで、水生動物にとっては大きな脅威となる。
中州、浅瀬、ヨシ原はほとんどなくなってしまい、動物は一気に海まで流される。
流速の遅い河川敷部にとどまったとしても、洪水がひけばそこは陸地である。
「河道整備=人工水路化」が生物にどのような影響を与えているのか、
今後の重要な検討課題である。
回遊動物の減少
河口堰運用前の長良川は、
川と海を行き来する回遊動物が豊富なことで知られていた。
回遊動物への影響予測も最大の論争点の一つであった。
国土交通省・水資源開発公団によってアユ溯上数が推定されているが、
堰建設・運用前のデータが少ないために河口堰の影響を評価することは困難である。
また、測定方法上も、測定地点より下流で放流されたアユのカウント、
洪水時に流下し再溯上するアユの再カウントなどの問題がある。
漁業統計や漁業協同組合へのアンケート結果では、長良川のアユ漁獲量は、堰運用後明らかに激減した。
ここでは、釣り人の長良川のアユに対する評価として、遊漁券の取得数の変化を示しておこう(図3)。
さらに、漁業統計では、ウナギ、モクズガニの漁獲は、堰運用前年に比べて、運用後5年間でほぼ半減した。
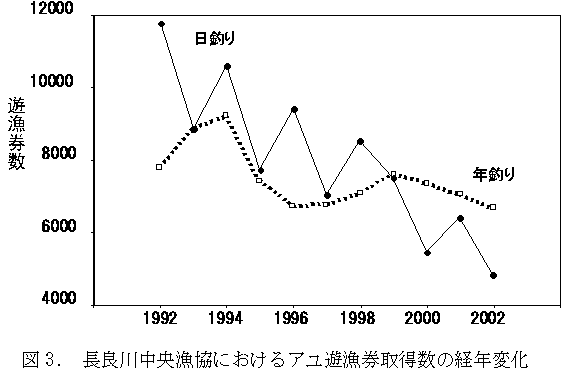
アユやサツキマスは毎年放流が行われており、放流魚が再生産に加わっており、
一定規模の個体群が維持されていることは事実であろう。
しかし、放流の行われていないカジカ(小卵型)、アユカケ、ヨシノボリなどの回遊魚ははどうであろうか?
国土交通省・水資源開発公団の調査から、カジカ、アユカケ、ヨシノボリが激減したことは明白である。
図4に河口から57km地点におけるカジカの調査結果を例示する。
木曽川、揖斐川ではもともとカジカの密度が低いので、木曽三川全体としてもカジカ個体群の将来が危ぶまれる。
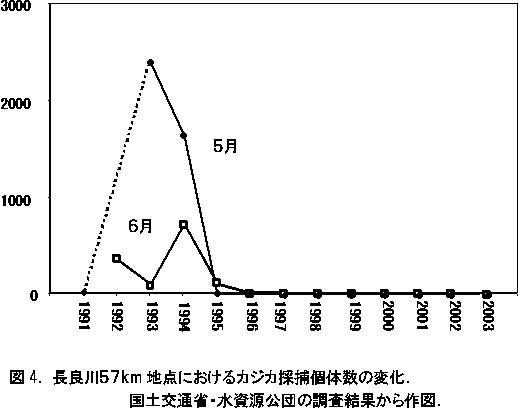
| Page 1・2・3・4・ | ネットワーク INDEX | HOME |
VOL31-3